この記事にはプロモーションが含まれます
windows10サポート終了の嘘つき説は本当?背景と真実を解説

windows10について「本当にサポートが終了するのか?」「嘘じゃなかったのか?」と疑問や不信感を抱いているのではないでしょうか。たしかに、かつてWindows 10は「最後のWindows」として発表され、多くのユーザーが新バージョンの登場はないと信じていました。ところが現実にはWindows 11が登場し、Windows 12のうわさまで出てきているのが現状です。
この記事では、「Windows 10は2025年以降どうなるのか?使えなくなるのか?」といった不安に対し、公式発表や現実的な影響をもとに整理していきます。また、「Windows 10のサポート終了後も使い続けるリスク」についての疑問や、「windows10のサポート終了・延長」の情報についても、最新情報をもとに詳しく解説します。
さらに、「Windows10からWindows11にアップデートすべきか?デメリットは?」「Windows 10とWindows 11の変更点」など、実際の使い勝手や違いについても触れ、今後の選択に役立つ情報をお届けします。もし、現在のパソコンがWindows 11に非対応であれば、「パソコン買い換えならいつが良いのか?」といった現実的な判断も必要になるでしょう。
最後に、windows11 サポート期限や将来的に登場が噂されるWindows 12まで、将来を見据えた情報もあわせてご紹介します。信頼できる情報をもとに、冷静に状況を整理し、あなた自身が最適な判断を下せるようサポートしていきます。
- Windows 10が「最後」とされた背景と方針変更の経緯
- サポート終了後に起こる具体的なリスクと影響
- 延長サポート(ESU)の仕組みと利用方法
- Windows 11や12への移行判断と注意点
windows10のサポート終了話が嘘つきと言われている件について

- windows10って最後じゃなかった?
- Windows 10のサポート終了後も使い続けるリスクは?
- サポート延長の可能性はあるのか
- Windows 11が非対応の場合どうする?買い換えならいつがベスト?
- Windows 10とWindows 11の変更点をわかりやすく解説
windows10って最後じゃなかった?

Windows 10は長らく「最後のWindows」として広く知られていました。2015年に発表された当初、マイクロソフトはこれを「サービスとしてのWindows」と位置づけ、今後は新バージョンのリリースではなく、Windows 10を基盤にした継続的なアップデートを通じて進化させていくと明言していたのです。
このように言うと、「Windows 10の後継は出ない」と捉えた人が多かったのも無理はありません。実際、当時の公式発表や開発者向けのコメントでも、Windows 11や12の登場については否定的な見解が示されていました。
しかし、その後2021年にWindows 11が突如発表されたことで、「Windows 10って最後じゃなかったの?」という声が一気に広がりました。これは当初の方針と異なる動きであり、多くのユーザーにとっては驚きだったと言えるでしょう。
この背景には、セキュリティ要件やパフォーマンス向上、UIの刷新など、Windows 10では対応しきれない技術的課題が浮かび上がったことが関係しています。たとえば、Windows 11ではTPM 2.0やSecure Bootのサポートが必須となっており、ハードウェアレベルでの安全性強化が図られています。これにより、Windows 10の設計を超える必要があったとも言えます。
こう考えると、「Windows 10が最後」という表現は、当時の方向性における考え方に過ぎず、技術の進化や市場のニーズによって柔軟に変更されるものだったと理解しておくのがよさそうです。
いずれにしても、マイクロソフトがその後の展開を完全に予測できていたわけではないという点は押さえておきたいところです。
Windows 10のサポート終了後も使い続けるリスクは?

Windows 10のサポートが2025年10月に終了することは正式にアナウンスされていますが、「それ以降も使えるのでは?」と考える人も少なくありません。たしかに、パソコン自体は急に動かなくなるわけではなく、基本的な操作やソフトの利用も引き続き可能です。
しかし、サポート終了後にWindows 10を使い続ける最大のリスクは、セキュリティアップデートが提供されなくなることです。
これにより、発見された脆弱性が修正されず、ウイルスやマルウェア、ハッキングなどの攻撃にさらされやすくなります。たとえば、過去にサポートが切れたWindows XPでは、標的型攻撃の被害が多発しました。
もう一つの問題として、サポートが終了したOSでは、新しいソフトウェアや周辺機器の互換性も次第に失われていきます。
プリンターやクラウドサービス、セキュリティソフトなどが順次対応を打ち切るケースが増えていくため、使用できる機能やサービスが制限される恐れがあります。
このような状況下では、企業利用はもちろん、個人利用においても安全性が大きく損なわれます。仮にインターネットに接続せずに利用するという選択肢もありますが、それは現代のPC利用環境では現実的とは言えません。
まとめると、
・セキュリティ
・互換性
の面だけで見ても、そのまま使い続けるのはリスクがあるということですね。
このため、Windows 10のサポート終了後もそのまま使い続けることは可能であっても、推奨できる選択ではないといえるでしょう。特にネットバンキングやオンライン決済を行うユーザーにとっては、リスクが高すぎるため、代替手段の検討が不可欠です。
サポート延長の可能性はあるのか

Windows 10の公式なサポート終了日は2025年10月14日とされていますが、「もしかしたら延長されるのでは?」と考える人も一定数いるようです。これは過去にWindows XPやWindows 7などのOSで、企業向けに有償サポートが延長された前例があるためです。
実際、マイクロソフトは企業向けに「Extended Security Updates(ESU)」という有料サポートプログラムを提供してきました。これにより、一般的なサポートが終了した後でも、セキュリティアップデートのみを継続して受け取ることが可能でした。
実は今回も個人ユーザー向けにも ESU(Extended Security Updates)が公式提供されています。
Windows 10 バージョン 22H2 を満たす端末で、次のいずれかの方法で登録すると、2026年10月13日まで「重要/緊急」のセキュリティ更新のみを受け取れます(機能追加・不具合修正・技術サポートは含まれません)。
- PC 設定のクラウド同期(Windows Backup)を有効化:追加費用なし
- Microsoft Rewards 1,000 ポイントを利用:追加費用なし
- 1 台あたり 30 米ドルの買い切り
登録には Microsoft アカウント(管理者) が必要で、ライセンスは最大 10 台まで流用できます。(Microsoftサポートの該当記事で確認可:Microsoft サポート)
一方、企業・教育機関向けの ESU は最長 3 年間(~2028年10月頃) 提供され、年ごとに価格が上がる有償モデルです(Year 1 の参考価格:61 米ドル/台)。
また、Windows 365 を利用して Windows 11 Cloud PC に接続する Windows 10 端末は 追加費用なしで ESU を受けられる特典があります。
なお、Microsoft 自身も ESU は移行のための一時的な橋渡しであり、長期利用を想定した恒久策ではないと位置づけています。したがって、過度な延長に期待するのではなく、Windows 11 への移行や PC 更新計画を進めるのが現実的です。
Windows 11が非対応の場合どうする?買い換えならいつがベスト?

現在使用中のパソコンがWindows 11に非対応である場合、今後の対応に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。実際、Windows 11の動作要件はやや厳しく、古いパソコンではTPM 2.0や第8世代以降のCPUが条件となっており、アップグレードができない機種が数多く存在します。
このような状況で選択肢は大きく分けて2つです。
ひとつは、Windows 10のサポートが終了する2025年10月まで使用を継続すること。
もうひとつは、新しいPCに買い換えてWindows 11へ移行することです。
買い換えのタイミング
まず、買い換えのタイミングについて考えるなら、「いつがベストか」は用途と今後の予定によって変わってきます。
例えば、今すぐにセキュリティやパフォーマンス面で問題を感じているなら、早めの買い替えが安心です。一方、現時点で安定して動作しており、サポート終了までの2年弱を慎重に使い切るという選択もあります。
ただ、ここで注意しておきたいのが、サポート終了が近づくとPCの買い替え需要が急増する可能性があるという点です。
特に企業などが一斉に導入を進めるタイミングでは、価格の高騰や品薄状態が起きやすくなります。
こうした混乱を避けるには、価格が落ち着いているうちに、性能とコストのバランスを見ながら段階的に移行を検討するのが賢明です。
もし、買い替えに金銭的な不安があるという方に、私は中古パソコンの検討をお勧めしています!詳しくは以下の記事をご覧ください。
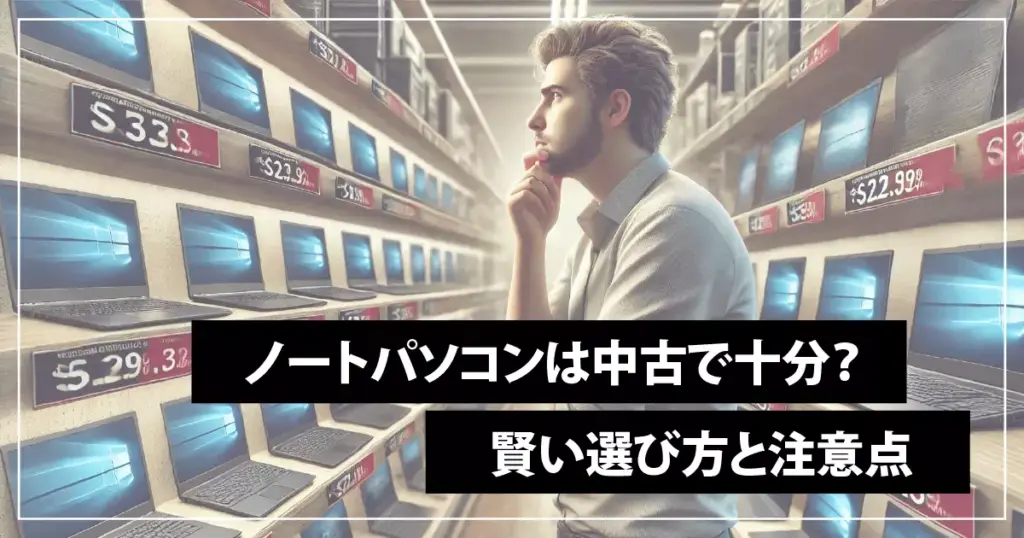
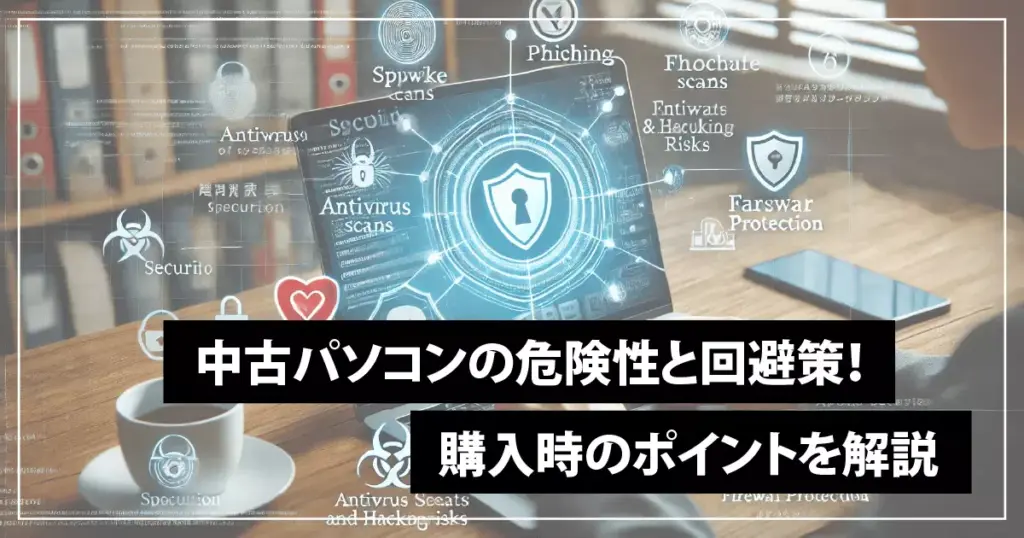
Windows 11を無理やりインストールする裏技について
また、買い替えを前提としない方法として「Windows 11 非対応のパソコンに無理やりインストールする裏技」も一部で話題ですが、マイクロソフトからの公式サポートが一切受けられない状態になるため、安定性やセキュリティ面でおすすめできません。
このように、現在使っているパソコンが非対応である場合は、すぐに買い替える必要はないものの、遅くとも2025年夏頃までには準備を始めておくことが重要です。焦らず、しかし確実に次の一手を検討していきましょう。
Windows 10とWindows 11の変更点をわかりやすく解説

Windows 10とWindows 11の違いは、単なるデザイン変更にとどまりません。見た目の刷新だけでなく、内部構造やセキュリティ、操作性などにも幅広い変化が加えられています。
まず、目に見えて分かるのがユーザーインターフェースです。
Windows 11ではスタートメニューが中央に配置され、全体的に丸みを帯びた柔らかいデザインになりました。タスクバーの構成もシンプル化され、モダンな印象が強まっています。これにより、スマートフォンやタブレットとの操作感の一体化が進んでいます。
次に大きく変わった点として、ウィンドウ操作の効率化が挙げられます。
たとえば「スナップレイアウト」という機能では、複数のウィンドウを自動で整理して画面上に配置できるため、マルチタスク作業がより快適になります。これまでフリーソフトに頼っていた人にとっては、標準機能で同等の作業環境が得られるのは大きなメリットです。
また、内部的にはセキュリティ強化も進んでおり、TPM 2.0の搭載やSecure Bootの標準化により、ウイルスや不正アクセスへの防御力が高まっています。これは企業ユーザーだけでなく、個人ユーザーにとっても安心材料となるでしょう。
ただし、新しい要件により古いパソコンでは対応できないケースも増え、移行のハードルが上がっている点には注意が必要です!
Windows 11では一部の古いアプリが動作しない可能性もあり、業務用途で特定のソフトを使っている場合には事前の互換性確認が欠かせません。
こうして比較してみると、Windows 11はただのマイナーチェンジではなく、次世代のPC体験に向けた土台となる設計が随所に見られます。とはいえ、すべてのユーザーにとって「絶対に必要」と言い切れるわけではないため、使用目的や現在の環境に応じて導入を慎重に検討することが大切です。
なぜ「windows10のサポート終了が嘘つき」と言われるのか?

- Windows 10は2025年以降、実際どうなる?使えなくなる?
- Windows 10からWindows 11にアップデートすべきか?デメリットは?
- windows11のサポート期限はいつまでなのか?
- Windows 12のうわさと今後の動向を整理
- サポート終了情報は本当に正しい?誤解を見極めるポイント
Windows 10は2025年以降、実際どうなる?使えなくなる?

現在Windows 10を使用されている方は、2025年10月以降どのような変化が訪れるか不安に感じるかもしれません。
サポートが終了すると、マイクロソフトからのセキュリティ更新プログラムや機能改善は提供されなくなります。その結果、ウイルスやサイバー攻撃に対して脆弱性が増し、安全面で重大なリスクが発生する恐れがあるのです。
一方、サポート終了後もPCがまったく動かなくなるわけではありません。
普通に起動し、アプリやインターネットにもアクセス可能です。しかしながら、セキュリティパッチが停止するため、新たに発見された脆弱性を放置したまま運用することは極めて危険です。オンラインバンキングやクレジットカードの利用、公共サービスへのアクセスなどが対象となるなら、セキュリティ対策の不備は大きな問題となります。
さらに、ソフトウェア開発者側もサポート対象外OSへ対応する意欲を失う可能性があります。そのため、最新アプリやブラウザ、ウイルス対策ソフトが対応を打ち切ることも考えられ、機能面の制限を感じる場面も出てくるでしょう。
このように、2025年10月以降は「使えなくなる」わけではないものの、安全性と機能面でのサポートが得られなくなり、実質的には使用継続が難しくなる可能性が高いと考えられます。
Windows 10からWindows 11にアップデートすべきか?デメリットは?

Windows 11へのアップデートを検討する際には、メリットと同時にデメリットも理解しておく必要があります。アップグレードに伴う主なメリットには、最新UIの導入やセキュリティ強化、マルチタスク機能の向上などが挙げられます。ただし、デメリットもいくつか存在します。
アップデート自体が不可能⁉
まず、古いハードウェアではアップデート自体が不可能な場合があります。
TPM 2.0や特定のCPU世代、Secure Bootの要件に満たないと、インストールできない仕組みになっています。このため、現在のPCが対応していなければ、アップデートを諦めざるを得ません。
操作感の違いに戸惑い
次に、操作感の違いに戸惑う可能性がある点にも注意が必要です。
スタートメニューの位置やタスクバーのデザインが変更されており、特に長年Windows 10に慣れたユーザーは、少し違和感を感じるかもしれません。
慣れれば効率的ですが、移行した直後は不便に感じることもあります。
互換性問題
また、一部の既存アプリや周辺機器が新しいOS環境に対応しておらず、動作しなくなるケースもあります。
業務で使用している特定ソフトや古いプリンタなどが対象となると、事前に互換性を確認する必要があるでしょう。
こうして考えると、Windows 11へのアップデートは多くの利点がある一方で、要件を満たすハードウェアが必要であり、操作性や互換性に課題があるため、慎重な判断が重要です。
windows11のサポート期限はいつまでなのか?

Windows 11のサポート期限は、バージョンごとに設定されており、一般ユーザー向けの各更新プログラム(機能アップデート)に対してHome/Pro等は各バージョン24か月、Enterprise/Educationは36か月のライフサイクルが設けられています。たとえば、バージョン21H2や22H2などが該当します。
このような更新サイクルを採用しているため、最新バージョンを維持している限り、次の期限まで一定期間はセキュリティ更新を受け取れる性質です。
ただし、古いバージョンを使い続けると、期限を過ぎると段階的にサポートが終了し、更新が停止してしまいます。
たとえば、バージョン21H2であればリリース日から約18ヶ月後には延長サポートが終了し、その後はセキュリティパッチが提供されません。バージョン23H2などではより長いサポート期間が設けられていますが、期限管理はユーザー自身が行う必要があります。
さらに、企業向けには延長オプションが提供される場合があるものの、個人ユーザーにはそのような仕組みは基本的にありません。
また、Microsoftの今後の方針変更により、サポート期間や仕組みが変更される可能性もあるため、最新情報には注意が必要です。
したがって、windows11を使う場合は、自分が使用しているバージョンのサポート期限を把握し、期限切れ直前に更新やアップグレードを行うことが望ましいと言えます。
| OS | サポート期限(米国時間) |
|---|---|
| Windows 11 バージョン 24H2 | 2026年10月13日まで |
| Windows 11 バージョン 23H2 | 2025年11月11日まで |
| Windows 11 バージョン 22H2 | 2024年10月8日まで →終了 |
| Windows 11 バージョン 21H2 | 2023年10月10日まで →終了 |
Windows 12のうわさと今後の動向を整理

Windows 12については、Microsoftからの正式発表はなく、あくまで噂や予想の段階です。
ただ、複数の報道によると、Windows 11を引き続き機能強化して提供する予定が2025年中にあるため、Windows 12のリリースは2025後半から2026年以降とされています。
AI技術をOSの中心に据える方向性が語られており、AI統合の強化や新しいUI設計、Androidアプリとの連携機能などが噂されています。
Microsoftは現在Windows 11の大型アップデート(例:24H2/25H2)に注力しており、Windows 12は少なくとも2025年中には発表されない可能性が高いです。
結論的に、Windows 12の存在自体は信憑性がありますが、時期や詳細は未確定であり、当面はWindows 11のアップデートに注力する可能性が高い状況です 。
サポート終了情報は本当に正しい?誤解を見極めるポイント

まず、Windows 10 のサポート終了日が 2025年10月14日 であることは Microsoft が公式に発表しています。
この日以降、セキュリティ更新や技術サポート、機能アップデートは一切行われなくなります。
しかし、「使えなくなる」とする誤解も多く見られます。
前述した通り、実際のところその日以降も Windows 10 は動作し続けますが、更新が止まることでセキュリティリスクが飛躍的に高まります。
次に重要なのは、Extended Security Updates(ESU)プログラムの存在です。
これは一定条件(Microsoft アカウントによる設定同期や OneDrive 使用など)を満たせば、2026 年10月まで無料で、または年間 30 ドルでさらに一年間のセキュリティ更新を受け取れる制度です。ただし、あくまでセキュリティ更新のみで、バグ修正や新機能、サポートは含まれません。
さらに、Microsoft 365 アプリに関しては、Windows 10 環境でも 2028 年10月までセキュリティ更新が提供される予定ですが、技術サポートは受けられなくなります。
誤解を避けるためには、以下のポイントに注意してください:
- 「動作しなくなる」わけではなく「更新されなくなる」ことが本質であること
- ESU による延長オプションがあるが、恒久的対策ではないこと
- Microsoft 365 アプリのセキュリティ更新は継続されても、OS 本体のサポートは終了すること
これらを踏まえれば、サポート終了に関する情報の多くが正確ですが、それを正しく理解し、的確に判断することが大切になります。
「windows10のサポート終了は嘘つき」と言われる背景と実態のまとめ
- Windows 10は当初「最後のWindows」と説明されていた
- その後、方針が変わりWindows 11が2021年に発表された
- Windows 10のサポート終了は2025年10月14日と正式に決定している
- サポート終了後もOSは動作するが更新は止まる
- セキュリティ更新が停止するため危険性が高まる
- 周辺機器やソフトが非対応になる可能性がある
- オンライン利用にはサポート終了後の使用は不向き
- 無料または有料で延長セキュリティ更新(ESU)を受ける方法がある
- 個人向けESUは条件を満たせば無料利用が可能
- 法人向けには3年間の有料延長サポートが用意されている
- Windows 11への移行には対応ハードウェアが必要
- Windows 11非対応PCのアップグレードには制限がある
- Windows 10と11ではUIやセキュリティ設計が大きく異なる
- Windows 12の登場は噂レベルで、現時点で公式発表はない
- 「使えなくなる」という誤情報が「嘘つき」との印象を生んでいる




